ビジネスをしていく上で決算書は避けては通れません。
決算書は確定申告を作成するためだけに作るものだと思っている方は多いと思います。
ですが、
決算書を読み取る力を身につけることでその会社の収益性や経営上の健康状態がわかるようになります。
ここでは決算書からわかることを解説していきます。
決算書とはなにか?
決算書は大きく分けて3つあります。
損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書です。
それらからどんなことがわかるのかを解説していきます。
損益計算書
損益計算書を見ることで、会社の一年単位の業績・収益性がわかります。
簡単に言うと,会社が儲かっているか儲かっていないかがわかります。
貸借対照表
貸借対照表を見ることで、会社の財務・安全性がわかります。
簡単に言うと,会社が潰れるかどうかがわかります。
キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書を見ることで、会社のお金の流れがわかります。
簡単にいうと,会社が伸びるかどうかといった会社の成長性がわかります。
以上の、決算書には主に3種類あります。
決算書の読み方のコツとポイント
決算書の種類がわかったと思います。
次にこの3つの決算書の読み方のポイントを解説していきます。
損益計算書の読み方のコツとポイント
損益計算書とは、売上から費用を引き最終的にどれだけの利益が出たのかが書かれている決算書です。
読み方のコツは、下記の3つの項目がどんな配分になっているかを把握することです。
✅売上(収入)
✅売上原価(商品仕入れや製造に係る経費)
✅販売管理費(店舗家賃・人件費・商品を販売する際に付随する経費)
ポイントとしては下記のとおりです。
✅売上はどうやって収入を得ているのかがわかる。
✅経費は、売上を得るためにかかる経費
(商品仕入・販売するために係る経費)がわかる。
経費での削減すべきとこや増やしてもいい経費がわかる。
大手企業の損益計算書の特徴とは!?
ファミリーマート
フランチャイズから主な売上を得ている。
ロイヤリティ収入で加盟店のコスト(商品の仕入費用)は反映されない。
マツキヨ
商品仕入れが多いので経費を占める割合は売上原価が大きい。
サイゼリヤ
原価(仕入)が30~45%で店舗運営費が多いのが特徴。
ZOZO
商品を預かり販売(受託販売)をしているため売上原価は低めの販管費が多め。
しまむら
メーカから仕入して店舗販売を行っているため売上原価が大きい。
ユニクロ
製造委託をして店舗販売を行っている。
貸借対照表の読み方のコツとポイント
貸借対照表とは、会社が健康か不健康かを判断する会社の診断書のようなもの。
資産、負債、資本で区分分けがされていて、下記の内容がわかります。
資産は、会社の財産。
負債は、会社が支払う義務のあるお金。
資本は、支払わなくてよいお金。
読み方のコツは、下記の3つの項目がどんな配分になっているかを把握することです。
✅資産(会社の財産)
✅負債(会社が支払う義務のあるお金)
✅資本(支払わなくてよいお金)
ポイントは下記のとおり。
✅会社の財産が一目瞭然でわかる。
✅会社が潰れないかどうかがわかる。
資産では、お金の使い方がわかる。
負債では、お金の集め方がわかる。
ちなみに集めたお金に返済義務があるのが負債です。
資本についても、お金の集め方がわかるが、こちらは返済義務がないのが特徴です。
例えば、
AさんとBさんがいて、
Aさんの貯金1,000万円、Bさんの貯金500万円
と仮定してどちらがお金持ちでしょうか?
としたときに、
単純にAさんと思いがちですが、
AさんとBさんの貯金の内訳をみてみると、
Aさんは借金800万円で純資産が200万円、
Bさんは無借金で純資産で500万円としたら、
Bさんのほうがお金持ちといえます。
こういったことがわかるのが貸借対照表です。
貸借対照表をもう少し細かく説明していきます。
資産の部では、
上から順に現金・預金とありますが、
これは1年以内に現金化できる財産の順になっており
下にいくごとに現金化しにくい財産
ということがいえます。
負債の部では、
上から順に買掛金・未払金とありますが、
これは1年以内に支払う義務のあるお金で
下にいくごとに長期借入金などの
1年以上支払わなくてよいお金
となっています。
資本の部では、
支払う義務のないお金となります。
例えば、
A社の場合
資産(現金・預金)>負債(1年以内に支払う義務のあるお金)
となると、経営状態が安定しています。
B社の場合
資産(現金・預金)<負債(1年以内に支払う義務のあるお金)
となると、
銀行から借入するとか財産を売らないと
お金が回らないという
自転車操業の状態です。
大手企業の貸借対照表の特徴とは!?
ゲーム業界
現預金を多く持つ。
製造は外部委託で借入金は少ない。
好業績で剰余金も多め。
百貨店業界
一等地に店舗を構え、リアル店舗が主で商品と資産が多い。
メルカリ
商品の販売代金はポイント化しており現金化するまでにタイムラグが発生する。
IT業に部類する。
ブックオフ
リアル店舗が主で商品と資産が多い。
キャッシュフロー計算書の読み方のコツとポイント
キャッシュフロー計算書とは、貸借対照表(健康診断書)の検査値といった感じです。
会社の1年間の現金の増減やお金がどうして増減したかがわかります。
キャッシュフロー計算書の構成は、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフロー、の3つに分けられます。
ポイントは下記のとおり。
✅お金の出入りの理由がわかる。
✅営業・投資・財務の三段階でお金の動きがわかる。
キャッシュフローの「キャッシュ」が指しているものは、現金・預金・現金同等物(すぐに換金できる価格変動リスクの少ない投資)で売掛金、受取手形、3か月未満の定期預金、投資信託などがあげられます。
決算書で会社の何がわかる?!決算書を読み解くポイント
例題①
会社が赤字続きであり、倒産するかどうかはどこでわかるか?
貸借対照表の資産と負債を比べればわかります。
資産<負債であれば
債務超過になるので倒産する可能性が高いです。
例題②
会社の成長性はどこでわかるか?
キャッシュフロー計算書で分かります。
キャッシュフロー計算書から投資・営業・財務の内容が読み取れます。
これは単独で見るより、組み合わせて判断することが大事です。
今後の成長が期待できる会社というのは、将来を見据えて投資する会社です。
例えば、
営業活動によるキャッシュフローで+(プラス)、投資活動によるキャッシュフローでー(マイナス)、財務活動によるキャッシュフローでー(マイナス)とした場合は下記のようなことが言えます。
営業活動キャッシュフローで+(プラス)ということは、本業でお金を稼げている。
投資活動キャッシュフローで-(マイナス)ということは、投資もできている。
財務活動キャッシュフローで-(マイナス)ということは、借金も返済できている。
以上を踏まえると成長性がある会社といえます。
例題③
借金が多い会社がありますが、倒産する危険性があるでしょうか?
借金が悪いとは限りません。
借金は会社の経営がうまくいっていないからと思いがちですがそうではありません。
借金にも良い借金と悪い借金があります。
良い借金というのは、借金をすることで大きな利益を生む商売ができるということです。
ただ注意点としては、会社の身の丈に合った借金に留めることです。
身の丈に合った借金の判断基準としては、貸借対照表の流動資産より短期借入金が多いか少ないかを見て多い場合は身の丈に合っていないです。
流動資産の全部で短期借入金を返せないからです。
決算書の読み方がわかるとメリットも!
決算書って聞くと小難しく感じる方は多いと思います。
ですが、全く難しくありません。
足し算・引き算・割り算・掛け算といった算数レベルのことがわかれば決算書を読み解くことができます。
決算書が読めるとメリットも多くあります。
決算書から数字がわかると会話やプレゼンで説得力が増す
会話やプレゼンを行うときに数字を入れて話すと説得力が高まります。
例えば、
商談の席で2パターンの会話。
①「このシステムを導入することで業務効率がとてもアップして残業時間の削減できます」
②「このシステムを導入することで業務効率30%アップが見込めて月20時間の残業が半分の10時間まで削減することができます」
商談を受ける側の人はどちらが魅力的だと感じるでしょうか?
パターン②のほうだと思います。
会話や提案するときに数字を入れることで具体的にイメージが湧き、説得力が増します。
まとめ
経営をしていく上で決算書を読み解く力は備えておくほうがよいことがわかったと思います。
決算書は学校でも会社でも読み方を習わないです。
ですので、自分で学んで覚えるしかありません。
決算書の数字が読めることで、営業・交渉・プレゼン・会議など
様々な仕事で役立ちますので、決算書が読めるようになることをおすすめします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。









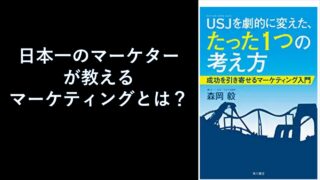
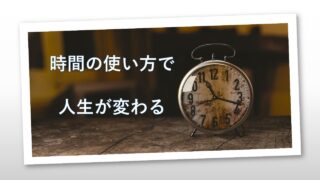


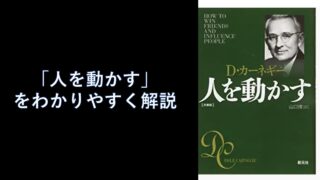





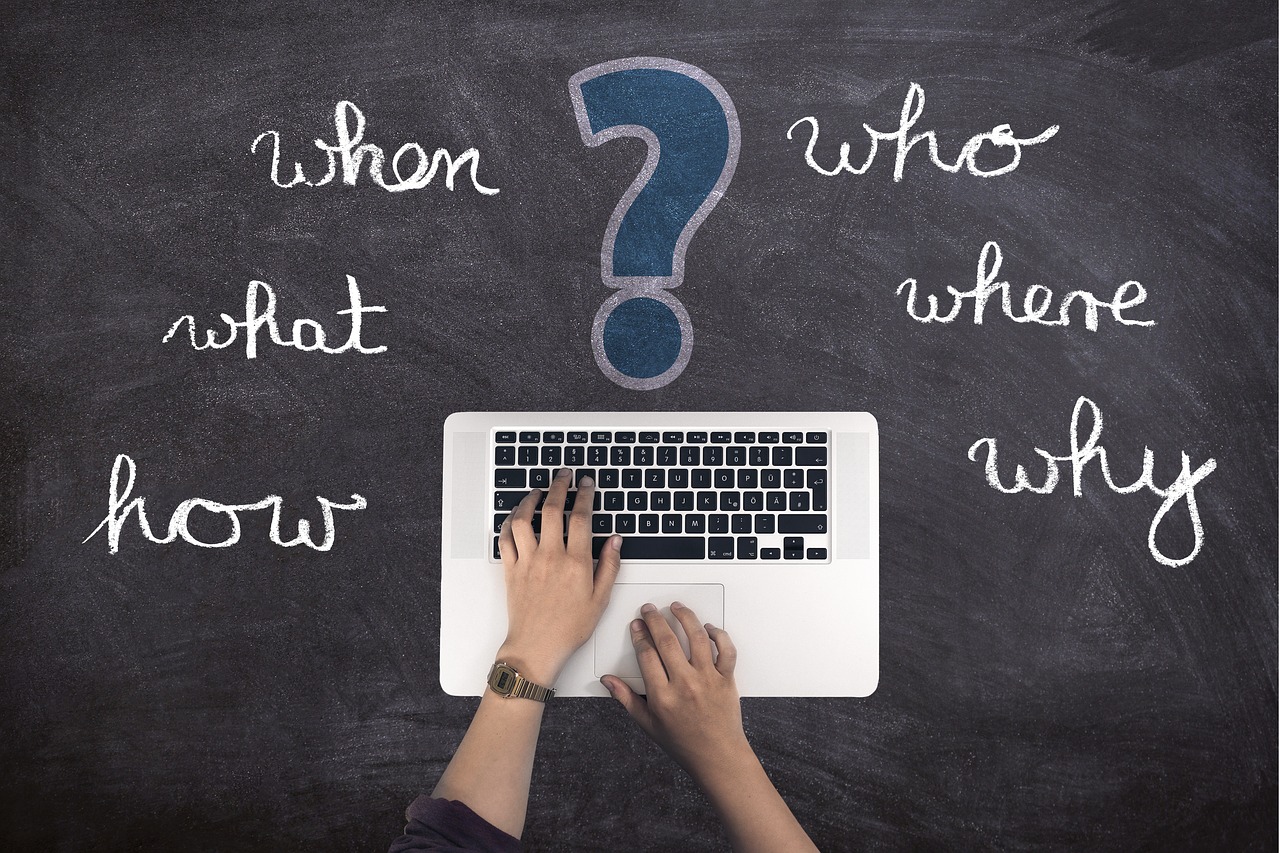




コメント